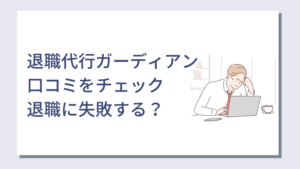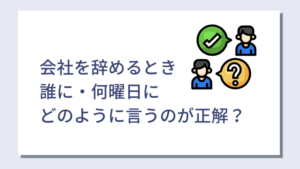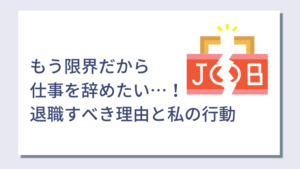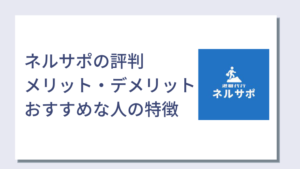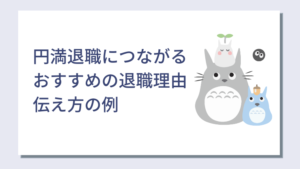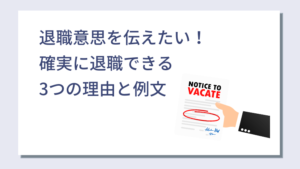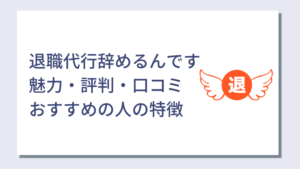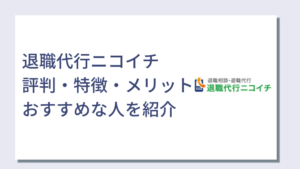退職すると、それまでの勤務先で加入していた健康保険の制度から脱退することになります。
日本は「国民皆保険」の制度なので、全ての国民は何らかの健康保険制度に加入していなければなりません。失業者も例外ではなく、会社を退職すると、すぐに新しい健康保険制度の制度に加入する必要があります。
そうしないと、病気やケガで病院に行ったときに、全額負担で払わないといけなくなってしまうからです。
その退職後の健康保険にもいくつかの選択肢があり、それぞれ加入条件や保険料が大きく違います。場合によっては年間30万円前後も保険料が変わってくることもあります。
退職後の健康保険には、原則として次の4つの選択肢があります。
- 国民健康保険に加入する
- 任意継続被保険者になる
- 家族の「被扶養者」になる
- 新しい勤務先の健康保険に加入する
今回は、これらの4つの選択肢のメリットとデメリットをまとめました。まずは、それらの制度のメリットとデメリットを知って、退職後の健康保険についての基礎知識を固めましょう。
退職後の健康保険4つの選択肢
退職後の健康保険の選択肢には、「国民健康保険」「任意継続被保険者」「家族の健康保険(被保険者)」「新しい勤務先の健康保険」の4つがあります。いずれかの健康保険に加入することで、引き続き3割負担で病院の治療を受けることができ、健康保険の各種給付も受けられます。
退職後の健康保険は、保険料などを比べて、最も有利なものを選ぶのが鉄則です。また、手続きの期限もあるため、遅れないように注意しましょう。それでは、それぞれの特徴と条件を見ていきます。
①国民健康保険に加入する
「国民健康保険」は、他の健康保険に加入していない人が対象の健康保険です。市区町村に資格取得届を提出して加入します。
大企業の「組合健保」や、中小企業の社員が入る「協会けんぽ(旧政管健保)」から脱退した後に、最初に選択肢の候補になるのが、自営業者などが入っている「国民健康保険」に加入するということです。
国民健康保険は、市区町村ごとに運営されています。法律で定められた基本的な給付内容は全国で同じですが、一部の給付を充実させている自治体もあります。
国民健康保険料は次の4つの要素のすべて、または一部を組み合わせて算出され、世帯主がその世帯の被保険者について、届出や保険料支払いの義務を負います。
- 所得割(世帯の所得)
- 資産割(世帯の資産)
- 被保険者均等割(世帯の人数)
- 世帯別平等割(世帯ごとに一律の額)
国民健康保険の計算方法は複雑で、市区町村ごとに算定の方法も異なります。正確な保険料は市区町村村役場の国民健康保険課に行けば、計算してくれるので、相談してみると良いでしょう。その際は、前年の所得証明書か確定申告書を持っていくとスムーズです。
国民健康保険は誰でも加入できますが、保険料が高くなるケースが多いというデメリットがあります。なぜかというと、保険料が、前年の所得に応じて算出されるからです。
失業している状態が長く続いてしまう場合、前年の(勤めていた時期の)収入で計算された保険料の負担は、非常に重く感じるかもしれません。
なお、国民健康保険の加入手続きは、退職の翌日から14日以内に市区町村の窓口に届け出ることになっています。これは任意継続の締切とは異なり、多少手続きが遅れても受け付けてもらえます。
◆国民健康保険◆
| 保険料 | 前年の所得で計算され、市区町村によって異なる |
| 加入条件 | 他の健康保険に加入していない |
| 手続き | 退職の翌日から14日以内に市区町村へ |
②任意継続被保険者になる
「任意継続」とは、元の会社の健康保険に継続加入するということです。保険料負担が軽くなるケースが多いのが、この「任意継続」という制度です。健康保険に2ヶ月以上入っていた人が退職したときには、2年間だけ在職中の健康保険を継続することができます。
原則として在職中の同様の保険給付が受けられますが、会社と折半だった「会社負担分」の保険料が全額自己負担となります。つまり、保険料がそれまでの2倍になるということです。
ただし、各健保組合では、多くの場合、上限が設定されていて極端に高くなるケースは少ないと言えます(上限があるため2倍になるとは限らない)。
例えば、中小企業の社員が加入する「協会けんぽ」では、任意継続の人の保険料の上限は月額2万2960円(40~64歳の人は、介護保険料込みで2万6124円)となっています。
これなら、年間約30万円で済みますが、①の国民健康保険に加入する場合、同じ条件の人でも年間60万円くらいかかる自治体もあります。それだけ、保険料は変わってくるのです。
任意継続被保険者になるには、退職の翌日から20日以内に健康保険組合などに申請しなければなりません。毎月の保険料は、その月の10日が締切です。
この2つの期限、「20日以内に申請」と「毎月10日までに支払い」は必ず守るようにしましょう。うっかり期限を越えてしまうと、任意継続できない、あるいは任意継続被保険者の資格を失うことになります。
あなたの会社の健康保険は、次のどちらでしょうか。健康保険証で確認できます。
- 協会けんぽ・・・中小企業の従業員向けに、全国健康保険協会が運営する健康保険(旧政管健保)
- 組合健保・・・大企業が設立した健康保険組合や、同業種の企業が集まって設立した健康保険組合が運営する健康保険
任意継続の申請は、自分の健康保険の加入先あてに行います。①の協会けんぽなら、協会の都道府県支部に郵送または持参します。
社会保険事務所の窓口でも預かってもらえます。②の組合健保なら、組合あてに提出します。
現在は健康保険も国民健康保険も、医療費の自己負担が同じ3割なので優劣がありません。任意継続するか国民健康保険に加入するかの判断は、以下の2点を踏まえた上で考えると良いでしょう。
- 給付内容に違いがあるか
- どちらの保険料が安いか
◆任意継続被保険者◆
| 保険料 | 会社負担分も自分で収める |
| 加入条件 | 退職日までに継続して2ヶ月以上健康保険に加入していた |
| 手続き | 退職の翌日から20日以内に、その健康保険組合などへ |
③家族の「被扶養者」になる
退職後の健康保険のもう一つの選択肢が、家族(配偶者や親など)の加入している社会保険に扶養親族として加入する方法です。
妻、または親や子供が働いている場合、保険料負担の面で一番ラクなのが、この「被扶養者」になるということでしょう。なにしろ、1円も払わずに健康保険に入れるのですから、非常にお得です。
被扶養者の条件は、「生計を維持されているか」と「同一世帯か」の2つです。配偶者や自分の親、子供などの被扶養者になるなら、同一世帯でなくても大丈夫です。
生計維持の基準は、まず自分の年収が130万円未満であること。そして、健康保険の被保険者と同一世帯の場合、自分の年収が被保険者の半分未満であること。被保険者と別世帯の場合は、自分の年収が被保険者からの仕送りよりも少ないことです。
年収や仕送りを証明する書類の提出が必要になります。健康保険の運営側にとっては、保険料という収入が増えずに給付の対象者が増えることになるため、通常、被扶養者の認定は厳しく行われます。なお、失業保険をもらっていると、原則として「被扶養者」にはなれません。
払うべき保険料ともらえる失業保険の額を比べれば、失業保険を受け取ったほうがお得なケースが圧倒的でしょうから、まずは失業保険を受け、そのもらえる日数(所定給付日数)が終了してしまったら被扶養者になるというのが、賢い選択肢になります。
◆家族の「被扶養者」になる◆
| 保険料 | 被扶養者の保険料負担はない |
| 加入条件 | 配偶者や親などに生計を維持され、年収130万円未満 |
| 手続き | 被扶養者になった日から5日以内に、被保険者が勤めている会社へ |
④新しい勤務先の健康保険に加入する
再就職ができたら、新しい勤務先の健康保険に加入することになります。もちろん保険料は労使折半になりますから、国民健康保険や任意継続のケースよりも負担は軽くなります。
早めの再就職は、生活が安定するうえに、失業保険の「再就職手当」がもらえ、さらに健康保険の保険料も軽くなるという「一石三鳥」だと言えるでしょう。
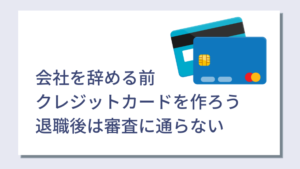
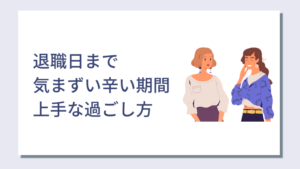
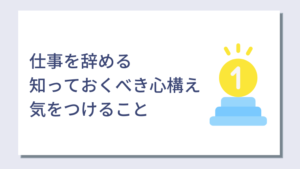
退職後の健康保険の任意継続とは?
健康保険の任意継続とは、退職や労働時間の短縮によって健康保険の被保険者の資格を失った際に、一定条件のもと個人で継続して健康保険へ加入できる制度のことです。任意継続すれば、会社員のときと同様の保険給付を受けられます。
健康保険を任意継続するためには、次の条件を満たす必要があることを知っておいてください。
- 被保険者の資格を失った前日までに継続して2ヶ月以上被保険者期間があること
- 被保険者の資格を失ってから20日以内に申請すること(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)
例えば、転職した職場を1ヶ月程度で退職する方は、継続して2ヶ月以上被保険者期間がない可能性があるため、健康保険を任意継続できない恐れがあります。
健康保険の任意継続の申請は、自宅の住所地を管轄する全国保険協会の支部で行います。任意継続において被保険者を継続できる期間は、任意継続被保険者となった日から2年間です。任意継続が永久的にできるわけではありません。
保険料を納付する際は、納付書による納付もしくは口座振替のどちらかを選べます。正当な理由がなく保険料を納付し忘れてしまうと、資格を失うことになります。支払いを忘れる可能性がある方は、口座振替によって自動的に支払えるようにするほうがよいでしょう。
退職後の健康保険料はいくらで加入できる?
退職後に健康保険を任意継続する際にかかる保険料は、「退職時の標準報酬月額×健康保険料率(9.33%〜10.51%)」で求められます。なお、40歳から64歳までの介護保険第2被保険者に該当する方は、介護保険料率(1.82%)が加わります。
なお、2023年12月時点では退職時の標準報酬月額が30万円を超えている場合、保険料を計算する際に標準報酬月額を30万円とみなすことを知っておいてください。
保険料は都道府県で一律ではなく、保険料率によって若干の変動があります。詳しくは、「都道府県毎の保険料額表」を参考にすることをおすすめします。
任意継続した保険料は、基本的に被保険者になってから2年間は変わりません。ただし、次の項目に当てはまる場合は、被保険者期間中に保険料が変動します。
- 健康保険料率や介護保険料率が変わったとき
- 標準報酬月額の上限が変更されたとき
- 健康保険料率が異なる都道府県へ転出したとき
任意継続した健康保険は、前納することが可能です。前納制度を利用して保険料を事前に一括で納付すると、保険料が割引(年4%複利原価法による)になります。
前納できる期間は、4月分〜9月分/10月分〜翌年3月分の6ヶ月分、もしくは4月分から翌年3月分の12ヶ月分です。年度途中で任意継続被保険者になった場合は、資格を取得した日の属する翌月分から、9月分または3月分までを前納できます。
任意継続か国民健康保険のどちらがお得?
基本的に健康保険は、これまでの収入によってかかる保険料が異なります。個人の収入によって任意継続と国民健康保険のどちらがお得になるのかは実際に計算してみなければわかりません。
多くの場合、収入が低い人は国民健康保険を、高収入と呼ばれる層の方は任意継続を選んだほうが保険料はお得になる傾向です。
以下では、任意継続と国民健康保険について次の項目に分けて紹介します。
任意継続のメリット
任意継続を選ぶメリットは、次のとおりです。
- 高収入の人は国民健康保険に入るよりも保険料が安くなる場合がある
- 健康保険の無加入期間をなくせる
- 前職の健康保険組合のサービスが利用できる
任意継続は、今まで会社負担であった保険料と自己負担分の保険料をどちらも納付する必要があるため、高くなるといわれることがほとんどです。しかし、保険料を算出する際の標準報酬月額には上限があることから、高所得者ほど任意継続を選んだほうが保険料を抑えられる可能性が高くなります。
健康保険の無加入期間をなくせることも、任意継続のメリットです。健康保険を任意継続しておけば、再就職するまでの期間に病気やケガをしても、医療費負担を軽減できます。一方で、転職先へ入社するまでに空白期間がある状態では、病気やケガをしたときに医療費が全額負担になることを知っておいてください。
健康保険を任意継続すると、前職の健康保険組合のサービスが利用できる場合があります。例えば、保養施設が利用できたり、人間ドックの受診補助を受けられたりするケースがあります。
任意継続がおすすめの人
任意継続がおすすめの人は、次のとおりです。
- 扶養家族が多い人
- 前職の収入が一般的に高収入と呼ばれていた人
- 独立して収入が上がる可能性が高い人
任意継続する場合、扶養家族の保険も対象として含みます。そのため、パートナーがいて、子どもが複数人いる世帯では、国民健康保険より任意継続するほうがお得になりやすいでしょう。
前職の収入が一般的に高収入と呼ばれていた人も、任意継続するほうがおすすめです。任意継続の保険料は、標準報酬月額をもとに算出します。標準報酬月額は上限が設けられており、上限以上稼いでいた人は、勤めていたときの標準報酬月額のすべてが保険料を算出する際に含まれるわけではありません。
そのため、国民健康保険へ加入するよりも任意継続を選ぶほうが保険料を抑えられる可能性が高いでしょう。
独立して収入が上がる可能性が高い人も、任意継続を選ぶことが適しています。国民健康保険は収入が上がるにつれて、保険料が高くなります。一方で任意継続したときの保険料は、前職の収入をベースにした金額です。
独立して収入が上がる見込みがある方は、前職の収入ベースで保険料が決まる任意継続を選び、保険料が高くなることを抑えるほうが得策です。
国民健康保険のメリット
国民健康保険のメリットは、主に次のとおりです。
- 所得が基準値を下回ると自動的に減額される
- 手続きが簡単にできる
国民健康保険は、前年度の所得をもとに算出されます。そのため、所得が前年よりも下回ると自動的に減額されることがメリットです。任意継続の場合、被保険者期間の2年間は収入が下がったとしても、一定額の保険料を納める必要があります。
ほかにも、国民健康保険は、取り扱いが市役所や区役所となるため、手続きを簡単に済ませられます。退職後は、さまざまな手続きで忙しくなるケースもあるため、簡単に手続きできる点は、国民健康保険のメリットといえるでしょう。
国民健康保険がおすすめの人
次の項目に当てはまる人は、任意継続よりも国民健康保険を選ぶことがおすすめです。
- 任意継続と比較したときに保険料が安くなる人
- 退職後しばらくは収入が落ち込む人
任意継続と比較したときに、保険料が安くなる人は、国民健康保険を選ぶことがおすすめです。おおよそ、300万〜450万円程度の年収の方は、任意継続よりも国民健康保険を選ぶほうが保険料は抑えやすい傾向です。
ただし、年度によって標準報酬月額の上限や都道府県次第で健康保険料率が異なるため、年間の保険料を一度計算してみることを推奨します。
退職後しばらくは収入が落ち込む人も、国民健康保険を選ぶほうがよいでしょう。例えば、退職後に働かない期間が生じる場合、任意継続の保険料を納めることが資金的に難しくなる恐れがあります。
国民健康保険は前年度の所得から保険料を算出するため、退職した年の収入が低ければ、翌年の保険料を抑えられるかもしれません。
退職後の健康保険に関するよくある質問
退職後の健康保険に関して、質問する場所が少ないため、悩みを抱える方は少なくありません。下記は、退職後の健康保険に関するよくある質問です。
以下では、各質問に対する答えを紹介します。
退職後の健康保険に入らない選択肢はある?
退職後に健康保険へ入らない選択肢はありません。日本では、国民皆保険制度によって健康保険へ加入することが義務付けられているためです。
退職後は、所定の方法に則って「任意継続する」もしくは「国民健康保険へ加入する」のどちらかを選ぶ必要があります。任意継続する場合は自宅住所を管轄する全国健康保険協会の支部で、国民健康保険へ加入する際は市役所や区役所で手続きします。
退職後の健康保険手続きでの必要書類は?
退職後の健康保険手続きでの必要書類は、任意継続と国民健康保険で異なります。それぞれで必要になる書類は下記のとおりです。
- 健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
- 退職証明書のコピーや雇用保険被保険者離職票のコピーなど
- 口座振替依頼書
- 世帯全員が記載された住民票(被扶養者がいる場合)
- 所得証明書(被扶養者がいる場合)
- 仕送りの事実が確認できる書類(被扶養者がいる場合)
- 健康保険等資格喪失証明書
- キャッシュカードまたは通帳・通帳使用印
- マイナナンバーと本人確認できるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)
加入する健康保険によって必要書類が異なることを知っておいてください。
14日以内の届出期間を過ぎた場合はどうすればよい?
国民健康保険に加入する14日以内の届出期間を過ぎた場合、加入すべき日までさかのぼって保険料を納める必要があります。なお、保険料をさかのぼる際は、最長2年分となっています。
届出が遅れたとしても保険料は納める必要があるため、退職後は、できるだけ早く届出を済ませることが大切です。
退職後の健康保険切り替えについてまとめ
退職後は、健康保険を切り替える必要があります。国内では、すべての国民が健康保険へ加入することが義務付けられているためです。
国民健康保険へ加入したり、任意継続被保険者になったり、被扶養者になったり、新しい職場の健康保険に加入したりすることが基本です。
退職後に一定期間仕事に就かない方や独立する方は、健康保険をどのように切り替えるべきか迷う方が少なくありません。国民健康保険もしくは任意継続のどちらかを選ぶ際は、前職の収入面に着目しましょう。
選択する目安として、平均よりも収入が低い方は国民健康保険を、高収入を得ているといわれる人は任意継続を選ぶほうが、保険料を抑えやすくなります。保険料は都道府県や年度によって若干の違いがあるため、どの方法で健康保険へ加入するのか迷う際は、試算することがおすすめです。




.png)