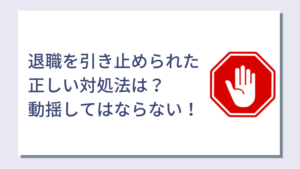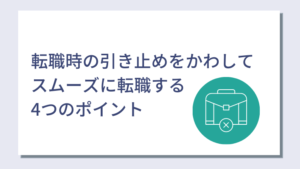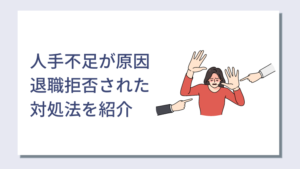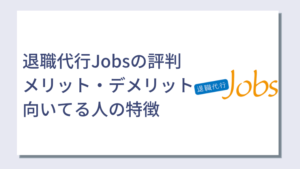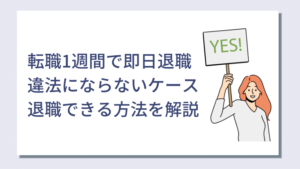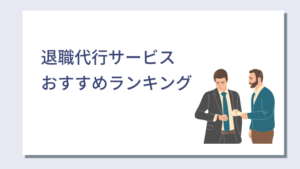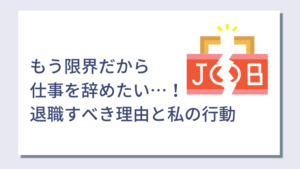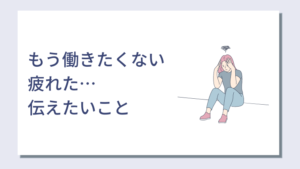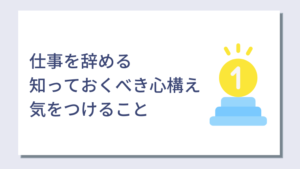「今すぐ会社を辞めたい!」「上司や同僚の顔を見たくない!」と焦るあまり、新卒の中には非常識な退職の切り出し方をしてしまうケースも多いもの。
また、社会人経験が少ないからこそ、退職に関しても誤った勘違いをしているケースも中にはいます。
しかし、円満に退職するのも社会人として大切な能力であり、次の就業先での活躍を左右する要素だといえるでしょう。
本記事では新卒向けに退職の切り出し方を中心に、ポイントを説明します。
あわせて絶対にやってはいけない退職の切り出し方もお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
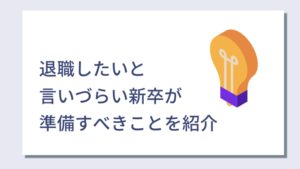
新卒が退職を伝える・切り出す前に押さえたい3つのポイント
いくら会社を去る意思があるとはいえ、今までお世話になったのには変わりありません。
円満に退職することで新しい職場でも、スムーズに仕事を進められるでしょう。
新卒が円満退職を行うために、退職を切り出す前に押さえたい3つのポイントをお伝えします。
辞意を伝えても、すぐには辞められない
新卒でよく勘違いしているのが「会社に辞意を伝えたら、ほぼ確実に辞められる」という考えです。
場合によっては「辞意を伝えたその日にでも辞められる」とさえ勘違いしている人も中にはいます。
しかし、自己都合退職でも上司から承諾されず会社から反対された場合は、スムーズに辞められない可能性があり、退職まで時間がかかることもあるでしょう。
後腐れなく会社を辞めるには「とにかく辞意さえ伝えたらいい」と見切り発車で進めてはいけません。
伝える相手やタイミングをしっかり見極め、言葉を選びながら慎重に進める必要があります。
まず最初に直属の上司へ辞意を伝える
退職意思を一番最初に伝えるのは、直属の上司です。
しかし、直属の上司と折り合いが悪いと、人事や直属の上司より立場が上の人に伝えたくなるものですよね。
ビジネスにおいて、退職意思を一番最初に伝えるのは直属の上司が常識です。
仮に直属の上司よりも先に別の社員に辞意を伝えてしまうと、部下のマネジメント能力不足として、上司の顔に泥を塗ることになってしまいます。
多少思うところがあっても、円満に退職するために、上司の顔を立てながら退職を進めていくのが良いでしょう。
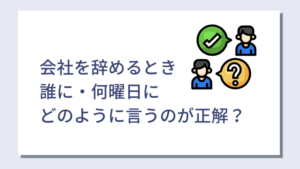
1ヶ月半〜2ヶ月前までには伝えるのがマナー
退職の意向は1ヶ月半〜2ヶ月前、遅くとも2週間前には伝えるのがマナーです。
民法上では、退職の意向を伝えてから2週間後には退職できると定められています(*)。
ただし、就業先の就業規則によっては、もっと早い段階で退職意思を切り出す必要がある場合もあるため確認が必要です。
あまりにも短すぎる場合は、円満に退職しにくい可能性があるため、なるべく時間に余裕をもって退職意思を伝えるのが良いでしょう。
(*)民法第627条第1項
ー当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。ー
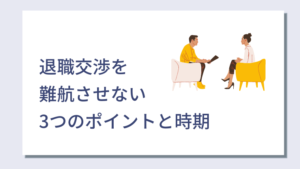
直属の上司に退職を切り出すタイミング
直属の上司に退職を切り出すタイミングは、業務時間外の人気の少ない時間帯がベストです。
タイミングを見計らって上司に「少々お時間よろしいでしょうか」と伝えましょう。
もし上司が忙しい場合は「来週10〜15分ほど、お時間いただけないでしょうか」と、事前にアポを取っておくのも良いでしょう。メールでアポを取っても問題ありません。
ここでのポイントは、アポ取りの際に退職の意向を伝えないことです。
退職の意向は、会議室などで上司と二人きりになったタイミングで伝えるものです。
アポ取りの段階で「今後の事についてお話があります」など、退職を匂わすような言葉を添えるのも良くないため、注意してください。
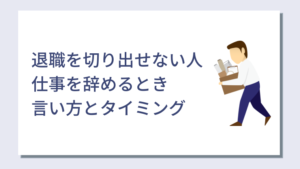
退職の切り出し方と伝えるべき3つの事項
直属の上司と会議室などで2人きりになれたら、退職の意向を伝えていきます。ここで必ず伝える必要があるのが以下3点です。
退職意思
直属の上司を個室に呼び出したら、まず最初に退職の意思を伝えます。
「突然で申し訳ありませんが、一身上の都合で退職させていただきたいと考えております」のように、お詫びの言葉を添えた上で、退職したい旨を伝えましょう。
「◯月◯日で退職させていただきます」と一方的に希望を伝える、あるいは「退職するか悩んでいるのですが…」といった相談のような切り出し方は良くありません。
このような切り出し方をすると相手の反発を買いやすく、強い引き止めにあう可能性も高くなり、トラブルに発展することも。
退職する意思があることはしっかり伝えながらも、なるべく上司の顔が立つように言葉を選んで退職意思を伝えていきましょう。
退職理由
退職の意思を伝えたらほとんどの場合、退職理由を聞かれます。
退職理由はなるべく前向きなものを伝えるのがベターです。
たとえ給料が安いといった会社の待遇面からの不満が原因でも、ネガティブな理由は出来るだけ伝えない方が良いでしょう。
もし待遇の不満を伝え「給料を上げるから会社に留まって」などと引き止められた場合、退職交渉が難航しやすくなります。
新卒で退職する場合は「若いうちに◯◯の経験を積みたいと考え、転職を決意しました」などの転職理由が一般的です。
今が退職するのにふさわしいタイミングであることと、現状だとその経験が積めない点を伝えられると良いでしょう。
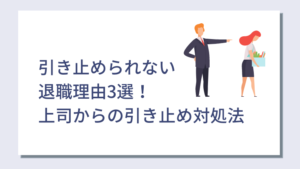
退職する時期
退職を切り出した際に、あわせて「◯月中の退職を考えております」といった、退職時期の目安も伝えておきましょう。
早い段階で目安となる退職時期を伝えておくことで、上司もメンバーの配置転換や引き継ぎのスケジュールなどの対応が行いやすくなります。
実際の退職日は上司や人事とともに決める必要があります。
必ずしも自分の希望とする退職時期で辞められるわけではないことを理解しておきましょう。
【NG】新卒がやりがちな退職の切り出し方
まだ社会人としては未熟な面も多い新卒。だからこそ間違った退職の切り出し方をしてしまう人も中にはいます。
では絶対してはいけない退職の切り出し方には、どのようなものがあるのでしょうか?
新卒がやりがちな退職の切り出し方NG例を紹介します。
メールやLINEで退職意思を一方的に伝える
メールやLINEで退職意思を伝えるのは一般的でないため、社会人の常識からは外れています。
最近は在宅勤務も増えてきて、なかなか上司と対面で会う機会が少ない人も多くなっていますが、できるだけ対面で辞意を伝えるようにしましょう。
対面が難しい状況であればZoomなどを活用し、オンライン上でも顔が見える状態で伝えるのがベターだといえます。
繁忙期など身勝手なタイミングで辞める
業務の引き継ぎをしっかり行った上で退職するのがマナーです。
繁忙期など通常よりも業務量が多い時期は、引き継ぎに時間が取りにくくなります。
そのため繁忙期で退職した場合、周囲に迷惑がかかる可能性が高く、反感を買われる恐れがあります。
各社繁忙期は異なるものの、年度末である3月末や、新入社員が入社する4月、半期の締めがある9月末、年末・仕事納めがある12月末などは、できるだけ避けたほうが良いでしょう。
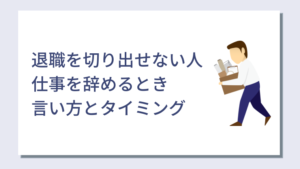
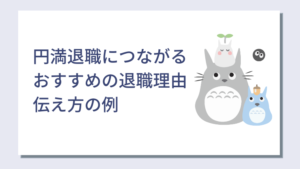
新卒が退職を伝えるときに注意するポイント
新卒が退職を伝えるときに注意するポイントを紹介します。退職を検討している方は、意識しておきましょう。
- 辞めると言い切る
- 引き止められても退職の意思を変えない
それぞれについて解説します。
辞めると言い切る
退職を伝えるときは、辞めると言い切ることが大切です。曖昧な表現や相談という形を取ってしまうと、上司から引き止められやすいです。
「まだなにもわかってない」「3年は続けた方が良い」「うちですぐ辞めるなら次行っても無理」など、辞めない方が良い理由を伝えられます。
新卒と比べて社会人経験が長い上司から「次の会社でも無理」といわれたら、「退職しない方が良いかも」と不安になるかもしれません。
しかし、退職を決意しているなら「◯月に辞めます」とはっきりと伝えることで、上司は「引き止めても無理だ」と思い、認めてくれやすくなります。
引き止められても退職の意思を変えない
退職を引き止められても、意志を変えないことが大切です。新卒で退職を伝えると「条件を良くする」「部署を変える」など、社内での良い条件を提示してくるかもしれません。
しかし、条件が良くなったとしても、「いつか辞めそうだな」と会社から思われるため、将来的に昇進や昇格ができない可能性が高いです。
もし、退職せずに残ることを決めた場合、新卒としての待遇は良くなるかもしれませんが、将来のことを考えると悪い選択です。
「退職を伝えるなら意志を変えない」「そもそも退職を伝えずに今の会社で頑張る」の、どちらかを選んだ方が良いでしょう。
新卒が退職を引き止められないようにする方法
新卒が退職を引き止められないようにする方法を紹介します。退職を伝えようと決意した新卒の方は参考にしてください。
- 次の職場が決まっていることを伝える
- 引き止められにくい退職理由を伝える
それぞれの方法を解説します。
次の職場が決まっていることを伝える
新卒が退職を引き止められないようにするには、次の職場が決まっていると伝えることです。次の職場が決まっていれば、「やりたいことが明確にあるから引き止めてもダメだ」と退職を認めてくれます。
また、次の職場が決まっている状態で引き止めてしまうと、他の会社の迷惑になるので上司も認めるしかありません。
引き止められにくい退職理由を伝える
退職を伝えるときに引き止められにくい理由を付け加えると効果的です。引き止められにくい退職理由は、以下のとおりです。
- 新しいスキルを身につけたい
- 会社を起業する
- 体調が悪い
- 親の介護で実家に戻る
- 結婚
「新しいスキルを身につけたい」「会社を起業する」など、なにか別のことに挑戦するような前向きな理由だと納得してもらいやすいです。
「体調が悪い」「親の介護」「結婚」など、やむを得ない理由の場合は、健康状態や家庭の事情になるので引き止められにくいです。引き止められにくい退職理由を、もっと知りたい方は下記記事の内容を参考にしてください。
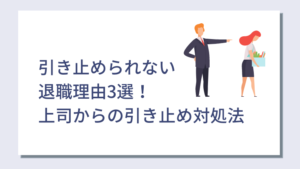
退職が切り出せないときは退職代行も検討
退職が切り出せないときは、退職代行の利用を検討しましょう。退職代行とは、本人の代わりに在籍する会社に退職の連絡をしてくれるサービスです。
本当に辞められるのか不安に思うかもしれませんが、退職できます。上司に引き止められたときに退職を貫き通す自信がない方は、退職代行を利用すると良いでしょう。
退職代行のサービスはさまざまありますが、退職代行ガーディアンの利用がおすすめです。退職代行ガーディアンを利用すれば、会社や上司への連絡を自分で行わず、即日退職できます。
料金は一律24,800円(税込)となっており、追加料金が発生する心配はございません。また、「東京労働経済組合」が運営しているサービスです。
労働組合が運営しているサービスであれば、退職の連絡だけでなく、「退職日」「有給休暇の取得」「退職金」など、条件の交渉を行ってくれます。
新卒で退職を決意したものの、上司に伝えられない方は退職代行ガーディアンに連絡してみましょう。
\会社との交渉も対応してくれる/
新卒は引き止められるのを覚悟の上で、退職を切り出すのがポイント
ここまで新卒向けに退職の切り出し方を中心に、新卒が円満退職するために押さえておきたいポイントを説明しました。
新卒はまだ社会人経験が少ないからこそ、退職に関しても誤った勘違いをしているケースも多く、焦りから非常識な退職の切り出し方をしてしまうことも。
いくら会社に不満があったとしても、これまでお世話になったのは事実です。
円満退職をすることで、次の就業先でも気持ちよく仕事を始められるでしょう。
退職を切り出す前におすすめしたいのが、転職活動を始めることです。
もし転職活動を始めずに退職を切り出すと、引き止めにあった時に流されやすくなってしまいます。
とはいえ働きながらの転職活動は時間的にも余裕がなく大変です。そんな場合は転職エージェントを活用するのも一つの方法です。