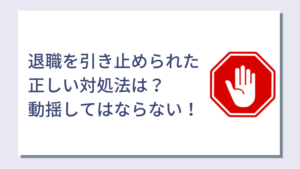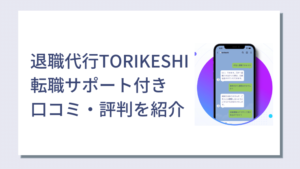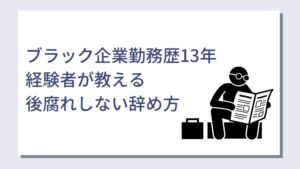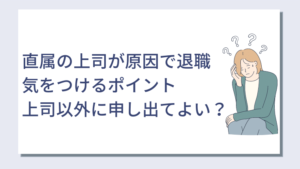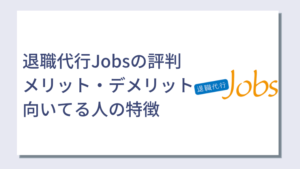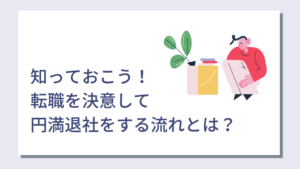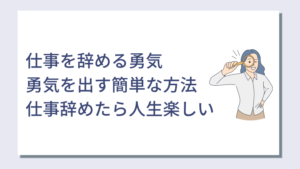テレビドラマでよくあるように、いきなり「辞表」を机に叩きつけて「本日で辞めさせてもらいます!」と言ってすぐに会社を辞められるわけではありません。
退職の意思は、最低でも退職の2週間前(現実的には1ヶ月半前)までに伝えるのがルールです。民法上では、退職の申し出から2週間を過ぎれば、たとえ会社がそれを認めなくても、法的には退職できるとされています。
実際には、会社の「就業規則」に規定があれば、それに従うのが一般的です。短期間での退職は引き継ぎが十分にできず、職場に迷惑をかけて辞めることになってしまいます。
どんな原因があろうとも、ケンカ別れのような形で退職してしまうと、転職した会社の人事担当者が前の会社に問合せをした際に悪く言われてしまい、転職先の会社に居づらくなってしまうかもしれません。
今回は、会社を退職すると決めたあなたが、いつ、誰に、どのように退職の意思を伝えれば良いのかを詳しく解説します。
会社を辞める決心はついても、そのことをなかなか上司には言い出しにくいものです。この記事をしっかり読み込んで、自分なりの退職の伝え方をしっかりと準備しておきましょう。
退職は「直属の上司」に伝えるのが理想
結論、退職する旨は直属の上司に伝えることが理想的です。その理由として、主に次の3つが挙げられます。
以下では、3つの理由について詳しく解説します。
ビジネスマナーとなっている
退職する旨は、直属の上司に伝えることがそもそものビジネスマナーとなっています。直属の上司を飛び越して、いきなり役員や人事部に退職する話を持ちかけることはルール違反です。
直属の上司の面子を潰す行為になってしまい、多方からよく思われません。また、ありもしない噂を流されてしまい、周囲との人間関係が悪くなる可能性もあります。
ルールを守らず退職手続きを進めると、円満退社ができなくなることが考えられます。組織の一員として動いている以上、適切な順序で退職手続きを進めてください。
業務に関する情報を滞りなく伝達するため
業務に関する情報を滞りなく伝達するためにも、退職に関する情報は直属の上司に伝える必要があります。
企業は組織として動いていることから、適切なところに必要な情報を伝えなければ、部署全体の業務が止まる原因になります。特に退職に関する話は欠員が出る内容にあたるため、直属の上司へ伝えることが不可欠です。
例えば、先輩や同僚に退職することを伝えた場合、直属の上司の耳に届くまでに時間がかかります。最悪の場合、内輪で話が止まってしまい、直属の上司へ退職する旨が伝わらない可能性も否めません。
退職することが適切に直属の上司へ伝わらなければ、退職希望日をずらさざるをえなくなり、勤め先および転職先のどちらにも迷惑をかけてしまいます。
直属の上司に早めに伝えることで適切な引継ぎができる
退職することが決まった際には、直属の上司へ早めに伝えることが重要です。退職する旨を早く伝えておくと、適切な引き継ぎができ、希望日に退職しやすくなります。
引き継ぎに余裕があると、引き継ぐ相手の負担を軽減することが可能です。自身も焦らなくて済むため、伝え忘れを防いだり、業務効率化に向けたアドバイスができたりします。
引き継ぐ相手は、自身の業務があるなかで退職者の仕事もこなさなければなりません。そのため、引き継ぐ期間が短いと不快に感じてしまうでしょう。また、部署内の業務を止めてしまう原因につながります。
円満退職したい方は、引き継ぎを逆算した上で退職することを伝える必要があります。
退職は上司に言う前に周りに言わない方がいい?
退職する旨は、上司より前に周りへ言わないほうがよいでしょう。周りに仕事を辞めることを話してしまうと噂が噂を呼び、ありもしないデマの情報を流されてしまう恐れがあります。
ほかにも、思わぬ形で退職する情報を上司が知ってしまう可能性も否めません。適切な流れで退職することが上司に伝わらなければ、残り少ない就業期間で上司との関係性がギクシャクする可能性があります。
無駄なトラブルを防ぐためには、退職することを上司へ伝え、上司から先輩・同僚へアナウンスしてもらうことがおすすめです。
上司への退職の伝え方
上司へ退職することを伝える際は、次のポイントを押さえておきましょう。
以下では、上司への退職の伝え方を詳しく紹介します。
2人きりの場を作ってもらう
上司へ退職することを伝える際は、2人きりの場を作ってもらうことが大切です。
上司と2人きりの場を作るときは、「お話ししたいことがあるため、ご都合のよいときにお時間をいただけないでしょうか?」と口頭で伝えましょう。
上司と話す予定を決める際は、メールを使わないようにしてください。メールにすると確認漏れが起きてしまい、退職する旨を伝えることが遅れてしまう原因になります。
退職する話は、情報漏洩を防ぐために会議室など、周囲へ音が漏れない場所を選ぶことがおすすめです。
くれぐれも、上司のデスクでいきなり「〇日に退職します」と伝えることは控えてください。退職する旨をいきなり伝えると、トラブルになったり、周囲へ配慮できない人間だと思われたりします。
1ヶ月前までには伝えておく
退職する場合、退職希望日の1ヶ月前までには伝えることがマナーです。仕事の引き継ぎや有休消化などを加味すると、1ヶ月程度の期間が必要になります。辞めることが決まっているのであれば、退職する旨を伝えるのは早ければ早いほど望ましいと言えます。
働いている状況で内定を得た場合は、現職で退職日を擦り合わせた上で、転職先へ入社希望日を伝えることが大切です。入社希望日から決めてしまうと、仕事の引き継ぎがうまくできず、引き継ぐ相手だけでなく、部署全体に迷惑をかけてしまいます。
転職先から入社日が指定されている場合は、直属の上司へ退職する旨を早急に伝えてください。
企業によっては、退職する旨を伝える時期が就業規則へ明確に記されている場合があります。退職することを決めているのであれば、事前に就業規則を読んでおくとよいでしょう。
退職する意思をはっきりと伝える
上司へ退職することを話すときは、意思をはっきりと伝えることが重要です。退職する意思をはっきりと伝えるためには、「退職します」と言い切る必要があります。
「転職しようと考えてまして…」や「転職すべきか迷っています」と曖昧な伝え方をすると、「話せば転職を辞めてくれる」と解釈されてしまうかもしれません。
どう切り出すべきか迷う方は、「本日は貴重なお時間をいただき、ありがとうございます。突然で申し訳ありませんが、退職させていただきます」と伝えるとよいでしょう。毅然とした態度で臨むと、より退職する意思がはっきりと伝わりやすくなります。
退職を伝える時の注意点
退職を伝えるときの注意点は、次のとおりです。
ここからは、2つの注意点を解説します。
上司に伝える退職理由を事前にまとめておく
退職する旨を上司へ伝えるときは、退職理由を事前にまとめておきましょう。上司に退職することを伝えると、必ずと言ってよいほど、「なぜ退職するのか」と聞かれます。
退職理由を明確に伝えられなければ、まともに取り合ってもらえない可能性があります。ほかには、上司から「退職する決意が固まっていない」と思われてしまい、引き止められたり、退職交渉が長引いたりする可能性もゼロではありません。
例えば、スキルアップを求めて転職する方であれば、「自分が思い描くキャリアを目指すために、より高度なスキルを身につけられる〇〇株式会社へ転職することにしました」と退職理由を伝えるとよいでしょう。
「なぜ退職するのか」と「退職後どうするのか」をセットで伝えられると、一貫性がある退職理由になります。
会社に対する不平不満を伝えない
上司へ退職することを話す際は、会社に対する不平不満を伝えないように配慮しましょう。
例えば、「待遇が悪い」「同僚が気に入らない」「将来性がない」などは、すべて会社に対する不平不満です。退職時に不平不満を口にすると、上司からの印象が悪くなり、円満退職できなくなることが考えられます。
また、不平不満を伝えると「〇〇を改善するから残って欲しい」と引き止められる口実になるかもしれません。
不平不満が理由で退職する場合は、本音ではない退職理由を伝えるほうがよいでしょう。
上司が原因で退職したいときは誰に言うべきか?
退職をする方のなかには、直属の上司によるパワハラやモラハラなどが原因で辞める人もいるでしょう。上司が原因で退職したいときは、上司以外に伝える方法をとっても問題ありません。退職したい旨を伝える先として、下記の2つがあります。
ここからは、やむをえず上司以外に退職を伝える方法について紹介します。
まずは人事部へ相談する
直属の上司が原因で退職したいときは、まずは人事部へ相談しましょう。この場合に限り、直属の上司へ最初に伝えなくても問題ありません。
人事部へ事情を説明した上で退職したい旨を伝えると、何かしらの手助けをしてくれる場合があります。例えば、上司もしくは自分を別の部署へ配置転換してくれるケースも見られます。
上司のパワハラやモラハラなどの事実を記録している場合は、社内問題として取り上げてくれることがほとんどです。被害の度合いによっては、訴えることができるかもしれません。
上司の上司へ相談する
直属の上司との関係性が悪い場合は、上司の上司へ相談する方法もよいでしょう。上司の上司へ退職する旨を伝える場合は、「なぜ直属の上司に話さないのか」「直属の上司のどのような部分が原因で退職するに至ったのか」などを伝えることが大切です。
周囲の同僚も直属の上司との人間関係に悩んでいる場合は、上司の上司へ退職する旨を伝えることで、職場で起こっている人間関係の不和を知ってもらうきっかけになります。
自分から退職を伝えることが困難な場合の伝え方
自分から退職を伝えることが困難な場合は、退職代行サービスを利用することがおすすめです。退職代行サービスとは、本人の代わりに弁護士や代行業者が退職手続きを進めてくれるサービスのことです。
利用料金がかかるものの、最短即日退職できる可能性があり、自らの口で退職したい旨を伝えられない方から支持されています。法律に則って退職手続きを進めてくれるため、退職代行サービスを使ったからと言っても勤め先とトラブルになることはほとんどありません。
退職代行サービスのなかでも、特に下記の3つは知名度が高いサービスとなっています。
「退職の話を上司が取り合ってくれない」「退職を告げることで嫌がらせを受ける可能性がある」という方は、退職代行サービスを使うことを視野に入れてみましょう。
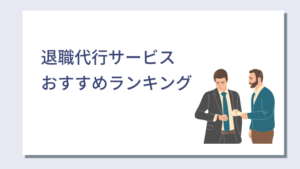
退職を伝えるのは基本的には「直属の上司」
退職する旨は、直属の上司に伝えることがビジネスマナーです。ほかの上司や同僚に退職することを伝えると、連携が取りにくくなったり、ありもしない噂を流されたりする恐れがあります。
上司に退職することを話す際は、はっきりと伝えることが重要です。曖昧な表現をしてしまうと、引き止められたり、退職交渉が長引いたりする原因になります。
「上司が原因で退職する」「上司に退職することを伝えにくい」という場合は、退職代行サービスの利用がおすすめです。退職代行サービスを利用すれば、上司と顔を合わせなくても退職手続きを進められます。