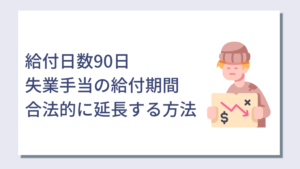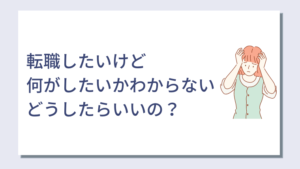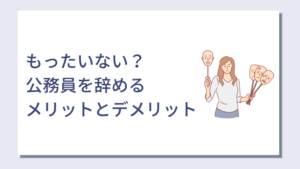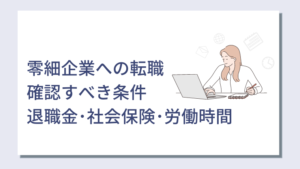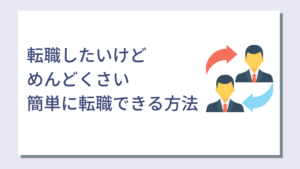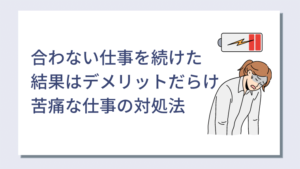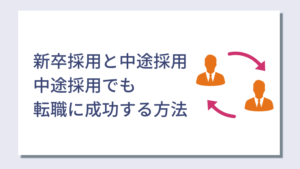失業中にもらえる給付金にはさまざまなものがありますが、給付金制度はわかりにくいものも多いため、失業中には少しでも損をしないように、給付金の制度をしっかりと把握しておくことが大切となります。
よく耳にする失業手当・失業保険と呼ばれるものは、「基本手当」のことを言いますが、他にも、職業訓練の受講手当や交通費、宿泊費などが支給される制度もあります。
また、「求職者支援制度」では、毎月10万円の給付金を受けながら職業訓練を受けることが可能です。
今回の記事では、失業中にもらえる給付金制度についてまとめました。
失業中の給付金は、自分から動かない限りもらえません。せっかくもらえるお金ですから、給付の条件や手続きの詳細は、ハローワークの担当者にきちんと確認し、損をしないようにしっかりと申請手続きをしましょう!
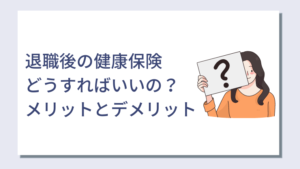
こんなにある!失業時にもらえる給付金制度
失業時にもらえる給付金制度について、1つずつ解説します。
基本手当
●どんな制度なのか
基本手当の仕組みは、受給金額×給付日数です。受給金額は、年齢や前職の賃金などにより受け取り可能な金額が変わります。
基本手当とは、雇用保険の一般被保険者であった人が離職し、失業した場合に国から支給される手当のことです。よく言われる失業手当や失業給付金とは、この基本手当のことを指します。
具体的な金額は、離職前6ヶ月間に支払われた賃金に基づいて計算され、離職前の賃金(賞与を除く)の50%~80%程度の金額が支給されます。
●対象者・手続き
受給条件は、就職しようという積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態であることです。
手続きは、失業者の住所を管轄するハローワークでおこないます(退職した会社の所在地ではありません)。
離職票や写真といった書類を提出し、失業と認定された場合に基本手当の受給が可能です。ただし、離職理由によっては給付資源機関が設定されることもあります。
なお、手続きに必要なものは、離職票、雇用保険被保険者賞、本人確認書類、写真、印鑑、本人名義の普通預金通帳です。
個別延長給付
●どんな制度なのか
個別延長給付は、厚生労働大臣が指定する地域で、倒産や解雇などの理由により離職した者(特定受給資格者)や特定理由離職者を対象とした基本手当の給付日数を延長する制度です。
離職日において45歳未満で就職困難な人や、知識、技能、職業経験などの実情を考慮して再就職支援が必要であると認められた場合に延長がおこなわれます。
延長日数の限度は60日(所定給付日数が270日、330日の場合は30日)です。
●対象者・手続き
個別延長給付は基本手当の給付日数の延長のため、基本手当受給の手続きをおこなった失業者の住所地を管轄するハローワークで延長の手続きをおこないます。
訓練延長給付
●どのような制度なのか
失業中の人が職業訓練を受け、スキルや知識を習得すると、就職の可能性が高まるだけでなく、今後の失業にも備えることができます。
そのため、職業訓練を受講する際に、労働者が、職業訓練に専念できるように、失業手当の支給を継続する「訓練延長給付」という制度が用意されています。
この制度を利用すると、所定給付日数が120日以下の人の場合は、失業手当の所定給付日数がまだ残っているうちに職業訓練を開始すると、訓練が終わるまで手当の支給が延長されます。
この制度を活用すれば、失業手当の所定給付日数が短い人でも、給付日数を増やすことが可能です。
●対象者・手続き
訓練延長給付を利用するには、ハローワークの受講指示が必要です。受講指示を受けるには、失業手当の受給手続きをしているハローワークで申し込みをおこないます。
申し込みを受けたハローワークは、職業訓練を受けることで就職が容易になると判断すれば、受講指示を出します。
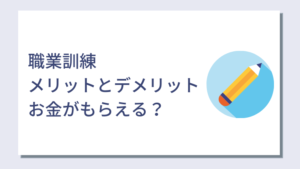
技能習得手当
●どんな制度なのか
職業訓練を受ける際に知っておきたい給付金が、雇用保険の技能習得手当です。
技能習得手当は、職業訓練を利用して失業中に新しい技術を身につけたいという人をバックアップしてくれるものです。
雇用保険の基本手当を受給する権利のある者(受給資格者)が公共職業安定所長の支持する公共職業訓練を受講する場合、その受給期間について、基本手当に加えて、技能習得手当が支給されます。
①受講手当
職業訓練を無料で受けながら、基本手当とは別に受講手当を受け取ることができます。受給資格者が公共職業安定所長の指示する公共職業訓練などを受講した日であって、かつ基本手当の支給の対象となる日について1日あたり500円(上限額2万円)が支給されます。
②通所手当
公共職業安定所長の指示する公共職業訓練等を受講するために電車やバスなどの交通期間を利用する場合に支給される交通費です。マイカーを使った場合も支給の対象となります。
原則として、片道2キロ以上ある場合に支給されます。支給額は、通所(通学)距離によって決められており、最高額は4万2500円です。
●対象者・手続き
公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受けることになったとき、すみやかに、受給資格者証とともに「公共職業訓練等受講届」および「公共職業訓練等通所届」を管轄のハローワークに提出します。
そのうえで失業認定の日に、受講資格者証を添えた公共職業訓練等受講証明書を管轄のハローワークに提出することで技能習得手当を受給できます。
寄宿手当
●どんな制度なのか
寄宿手当は、職業訓練等を受けるため、家族と別居して寄宿する場合に支給される制度です。
受給金額は月額1万700円です。
●対象者・手続き
手続きに必要なものは、公共職業訓練等受講届および公共職業訓練等通所届、受給資格者証です。支給の対象は、求職者によって生計を維持されている同居の親族と別居する場合に限られます。
求職者支援制度
●どんな制度なのか
2011年10月より開始された給付金制度です。雇用保険を受給できない求職者に対して無料の職業訓練や給付金の支給、ハローワークによる就職支援などをおこないます。
受給金額は、訓練受講期間中に月10万円+交通費が支給されます。各職業訓練のコースには、3ヶ月~6ヶ月のものがあります。
●対象者・手続き
受給条件は、ハローワークに求職の申し込みをおこなっていること、雇用保険に加入中でないこと、または失業手当を受給していないこと、働く意思と能力があること、職業訓練が必要であるとハローワークが認めたこと、などです。
再就職手当
●どんな制度なのか
再就職手当は、失業者が早期に就職先を見つけた場合に支給される手当のことです。再就職手当の金額は、以下の計算式で決まります。
▼基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合
所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額(上限あり)
▼基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合
所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(上限あり)
また、再就職後の賃金が下がった場合、新しい職場に6ヶ月間定着することを条件として、賃金の下がった部分の6ヶ月文(上限は基本てあたの支給残日数の40%)が、一時金(就業促進定着手当)として上記手当に加えて支給されます。
●対象者・手続き
再就職手当の支給申請書に必要事項を記入し、ハローワークに提出します。この申請書には、再就職先の事業主の署名、押印が必要なので、あらかじめもらっていくようにしましょう。
手続きに問題がなければ、基本手当が振り込まれていた口座と同じ口座に再就職手当が振り込まれます。
就業手当
●どんな制度なのか
再就職手当を受給するためには「1年を超えて勤務することが確実」と見込まれる再就職先を見つけなければいけません。
しかし、中には、正社員ではなく、他院機関のパートや派遣社員、契約社員の形で働くことになる人もいます。
そこで、こうした再就職手当の受給要件に該当しない場合であっても、就職先を見つけた人に支給されるのが就業手当です。
●対象者・手続き
就業手当の受給条件は、常用雇用など以外の形態の職業に就いた場合に、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合です。
受給金額は、基本手当の支給残日数と基本手当の日額により決定されます。
常用就職支度手当
●どんな制度なのか
常用就職支度手当は、就職が困難な人が支給日数がにこっている受給期間内にハローワークの紹介で安定した職業についた場合に、基本手当に日額の40%を支給する制度です。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合には再就職手当の対象者となるため、常用就職支度手当の対象者は、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満の者ということになります。
●対象者・手続き
常用就職支度手当を受給する場合、新たな就職先が決まったあと、事業主から証明を受け、「常用就職支度手当支給申請書」を申請者の住所を管轄するハローワークに提出します。
広域求職活動費
●どんな制度なのか
広域求職活動とは、雇用保険の失業など給付の受給資格者がハローワークの紹介で、そのハローワークの管轄区域外にある会社などの事業所を訪問したり、面接を受けたり、事業所を見学したりすることを言います。
広域求職をおこなう失業者に支給されるのが、雇用保険の広域求職活動費です。
交通費(鉄道、バス、船賃、タクシー代など)や宿泊費が必要に応じて支給されます。手続きに必要なものは、広域求職活動費支給申請書、受給資格者証などです。
移転費
●どんな制度なのか
ハローワークで紹介された職業に就くため、もしくは職業訓練を受講するために住所(居所)を変更する必要がある場合、移転に必要な費用が支給される制度です。
移転費には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、移転料、着後手当の6種類あり、旧居住地から移転居住地への移転費用が必要に応じて支給されます。
移転費支給申請書、受給資格者証などが手続きの際に必要になります。また、移転したあと、すぐに就職先の事業主に対して移転費支給決定書を提出する必要があります。
高年齢求職者給付金
●どんな制度なのか
65歳以降に退職すると、失業など給付の種類は基本手当ではなく高年齢求職者給付金という一時金に変わります。受給金額は、基本手当の50日分(被保険者として雇用された期間が1年未満のときは30日分)の給付金が一括で支給されます。
対象者・手続き
受給資格は、原則として離職の日以前の1年間に、被保険者期間が6ヶ月以上あることが必要です。高年齢求職者給付金を受ける手続きは、基本手当のときと同じです。
給付金の受給期間は1年と決められています。求職の申し込みの手続きが遅れた場合、失業認定日から受給期限までの日数分しか支給されません。
高年齢雇用継続基本給付金
●どんな制度なのか
労働の意欲と能力のある60歳以上65歳未満のものの雇用の継続と再就職を援助・促進していくことを目的とした給付が高年齢雇用継続給付です。
●対象者・手続き
高年齢雇用継続基本給付金が支給されるのは、60歳以上65歳未満の一般被保険者です。
被保険者(労働者)の60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、各月の賃金額が75%未満に低下した状態で雇用されている場合に、支給されます。
受給する場合、本人または事業者が、「高年齢雇用継続給付支給申請書」と「払渡希望金融機関指定届」および「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」などの添付書類を事業所の所在地を管轄するハローワークに提出します。
高年齢再就職給付金
●どんな制度なのか
高年齢雇用継続給付のうち、高年齢者の再就職を支援する目的での給付が高年齢再就職給付金です。
●対象者・手続き
雇用保険の基本手当を受給していた60歳以上65歳未満の受給資格者が、基本手当の支給日数を100日以上残して再就職した場合に支給されます。
受給するためには、雇い主である事業主が、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」「(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」と「払渡希望金融機関指定届」を作成し、添付書類と一緒に事業所の所在地を管轄するハローワークに提出します。
国民健康保険の保険料減免
●どんな制度なのか
国民健康保険には、倒産やリストラなどの非自発的理由で失業によって加入した人の保険料を軽減する制度があります。
国民健康保険は前年の所得などをもとに保険料を算出しますが、この制度では、前年度の所得を3割とみなして計算するため、その分だけ保険料が安くなります。
軽減が受けられる期間は、退職日の翌日から翌年度末までです。
ただし、再就職が決まり、会社の健康保険に加入した場合は、国民健康保険を脱退するため、軽減措置は終了となります。
●対象者・手続き
対象者は、雇用保険の特定理由退職者と特定受給資格者で、65歳未満の人です。特定受給資格者とは、倒産、リストラ、セクハラやパワハラを受けた、実際の労働条件が契約と大きく異なっていたなどの理由で退職した人です。
特定理由退職者は、病気やケガ、体力不足、労働契約の雇い止め、親族の扶養や介護が必要になったなどの理由で退職した人のことです。
国民年金の保険料免除制度
●どんな制度なのか
自分で直接保険料を納付することになっている第1号被保険者の場合は、経済的に困窮していて、保険料を払えないということもありえます。
そのような場合のために、救済措置として「保険料免除制度」が設けられています。
保険料の免除には、「法定免除」と「申請免除」があります。法定免除は、障害基礎年金をもらっている人や生活保護法に基づく生活扶助を受けている人などのための免除制度です。
申請免除は、前年の所得が少ないなど、経済的な理由で保険料を納めることが困難な人のための免除制度です。
●対象者・手続き
申請免除には、保険料の全額が免除される「全額免除」と、保険料の4分の3が免除される「4分の3免除」、半額が免除される「半額免除」、保険料の4分の1が免除される「4分の1免除」があります。
第1号被保険者、配偶者、世帯主で、保険料を納付することが困難なときは、住所地の市区町村役場で申請して承認を受け、免除の内容に応じて保険料が免除されます。
所得税の還付
●どんな制度なのか
1ヶ月の収入が一定額を超えると、給料から所得税が源泉徴収されます。しかし、1年間の収入が103万円以下だったり、生命保険などに加入している、扶養家族が増えたなどの事情がある場合、1年間の収入で計算すると、源泉徴収された租特税が収め過ぎになることがあります。
そのような場合、還付申告をすれば納めすぎた税金が返ってきます。
●対象者・手続き
会社員などの場合、年末調整の手続きをすれば、源泉徴収された税金の還付を受けることができます。
しかし、1年間の医療費の負担額が一定額を超えていて医療費控除を受けたい場合や、年の途中で退職して年末調整を受けていないといった場合、確定申告によって還付申告をする必要があります。
書類は税務署などの窓口に取りにいくか、国税局のホームページからダウンロードすれば、入手することができます。提出は税務署の窓口に直接持参するか、郵送します。一定の手続きをすればインターネットでも提出できるようになります。
還付金の請求は、1年間いつでもおこなうことができますが、請求できる日から5年間の間におこなわないと時効により請求権が消滅しますので注意してください。
傷病手当金
●どんな制度なのか
労働者(被保険者)が業務外の病気やケガで働くことができなくなり、その間の賃金を得ることができないときに、健康保険から傷病手当金が支給されます。
傷病手当金の支給額は、1日につき標準報酬日額の3分の2相当額です。
ただし、会社などから賃金の一部が支払われた場合は、傷病手当金と支払われた賃金との差額が支払われます。傷病手当金の支給期間は支給会社から1年6ヶ月です。
1年6ヶ月経過すると傷病手当金の支給は打ち切られますが、1年6ヶ月後も障害が残っている場合には障害年金が支給されることになります。
●対象者・手続き
傷病手当金を受給するためには、療養のために働けなくなり、その結果、連続して3日以上休んでいたことが要件となります。
「療養のため」とは、療養の給付を受けた(健康保険などを使って病院などを受診した)という意味ではなく、自分で病気やケガの療養をおこなった場合も含みます。
「働くことができない」状態とは、病気やケガをする前にやっていた仕事ができないことを指します。
損をしないように知っておこう!
やむ終えず会社を辞めることになったり、退職してからなかなか転職先が見つからないなど、失業してしまったときには、今後のことが不安になってしまうものです。
そんなときに大いに活用できるのが、国や地方自治体の職業訓練や各種給付金制度です。
給付金制度や、職業訓練制度は「知っている」と「知らない」では後々の生活に大きな違いが出てくる場合もあります。
少しでも損をしないように、失業中にもらえる給付金制度や職業訓練のことを知り、今後の生活のために役立てることができれば幸いです。